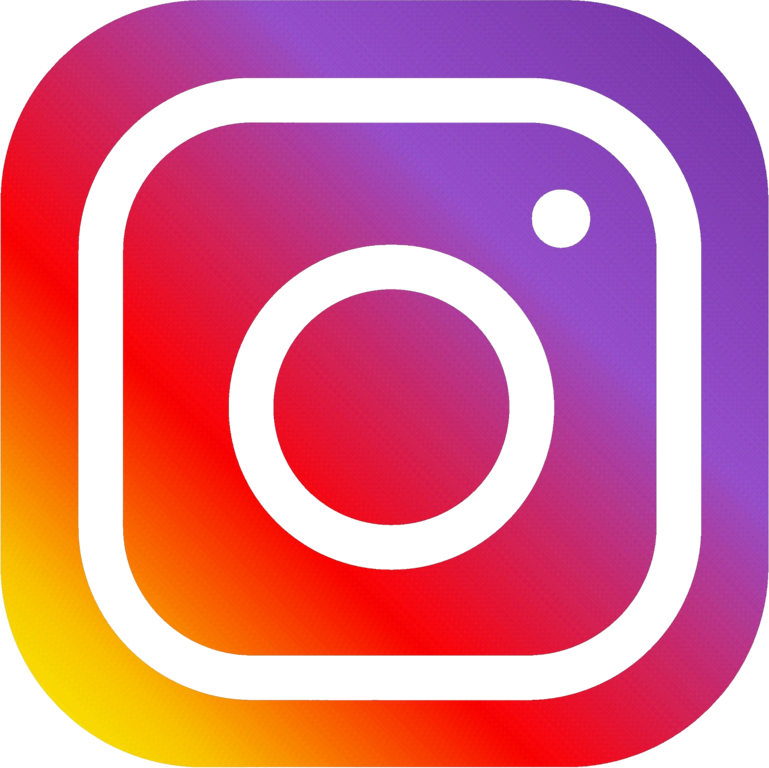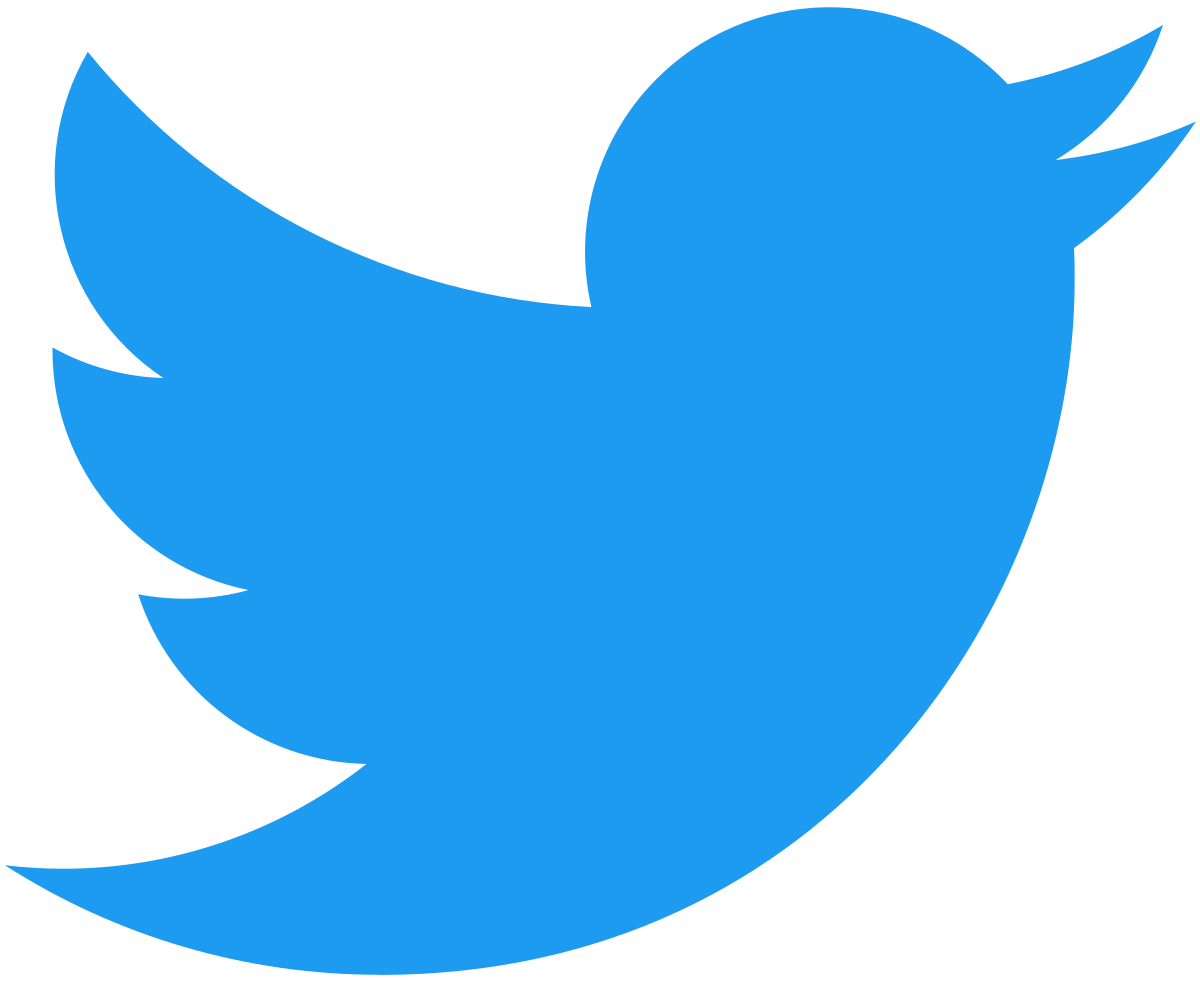中世の条約に逆行する米国とトランプ氏
-

英王室の馬車に乗った同国のチャールズ3世国王とトランプ米大統領
第2次トランプ政権において米国の外交政策には根本的な転換が見られ、通常なら議会による正当性確認が必要であった国際条約が個人的な合意へと変化しました。
アメリカの外交専門誌『フォーリン・ポリシー』は最近、ある記事において「第2次トランプ政権におけるアメリカの外交政策では伝統的なルールに基づくプロセスが放棄された。憲法によれば議会による正当性承認が必要とされていた国際条約は、大統領と外国首脳の間の個人的な合意へと変貌している」と指摘しています。
【ParsToday国際】これらの合意は表面的には外交上の成果として提示されているものの、実際には個別の取引に近く、確固とした法的・制度的根拠が欠如しています。このような変化は、条約が国王の意志と存続に結びついていた中世のモデルを彷彿とさせるものです。
アメリカの政治的慣習では、主要な条約は上院の3分の2以上の賛成、または下院での過半数の賛成によって批准・承認され、大統領が単独で国家の運命を変えることはできないとされています。しかし今日のアメリカでは議会の介入なしに数十もの合意が発表され、実質的に大統領が唯一の外交政策主体となっています。まさにこの状況を防ぐべく、アメリカの建国の父となった人々は抑制と均衡のシステムを設計していました。
問題は、こうした合意が財政負担や軍事的関与を強いる可能性がある一方で、予算権限と戦力の大部分が米国議会に委ねられている点です。国民の代表による投票を経ない合意は国内法上の正当性を欠き、国際法上も疑問視される可能性があります。そのため、こうした約束事や取り決めの多くは、実際には不安定な基盤の上に成り立っていることになります。
もう一つの側面は、広範囲にわたる秘密主義です。合意・協定の多くは公表されておらず、議会議員でさえその詳細を把握していないのが現状です。この状況は、20世紀に幾度となく国際的な危機を引き起こした秘密条約と酷似しています。場合によっては、合意締結に当たった当事者がアメリカ政府の主張を否定することもあり、国内外の不信感を高めています。
これが現実の問題であることを示す具体的な実例としてウクライナの鉱物資源協定、中米エルサルバドルと西アフリカ・ガーナの移民帰還協定があり、これらは合意内容が長期間隠蔽された事例です。これらに関連する裁判では、最高裁判所でさえ証拠文書不足に直面し、最終的には政府が措置を講じることのできる暫定命令の発令を迫られました。このプロセスは、法の透明性の欠如が深刻な混乱を招き得ることを示しています。
こうした道を歩み続けることは極めて危険です。その理由は、大統領の個人的な合意が正式な条約に取って代わってしまうからです。つまり、ホワイトハウスのメンバーが交代するたびに、アメリカの対外的な約束や取り決めも覆されることになります。このような状況はアメリカの同盟国にとって不安定さのしるしと言えるもので、アメリカのライバル国にとっては格好の好機となりかねません。
歴史的な経験は、条約が立法機関によって裏付けられている場合にのみ持続可能であることを物語っています。それ以外の場合、条約は一時的な合意のようなものとなり、1人の考えが変われば崩壊してしまいます。これゆえ、アメリカ建国者らは「条約の権限を一人の人物に集中させることは、国を選択性君主制に導くことになる」と警告してきたのです。