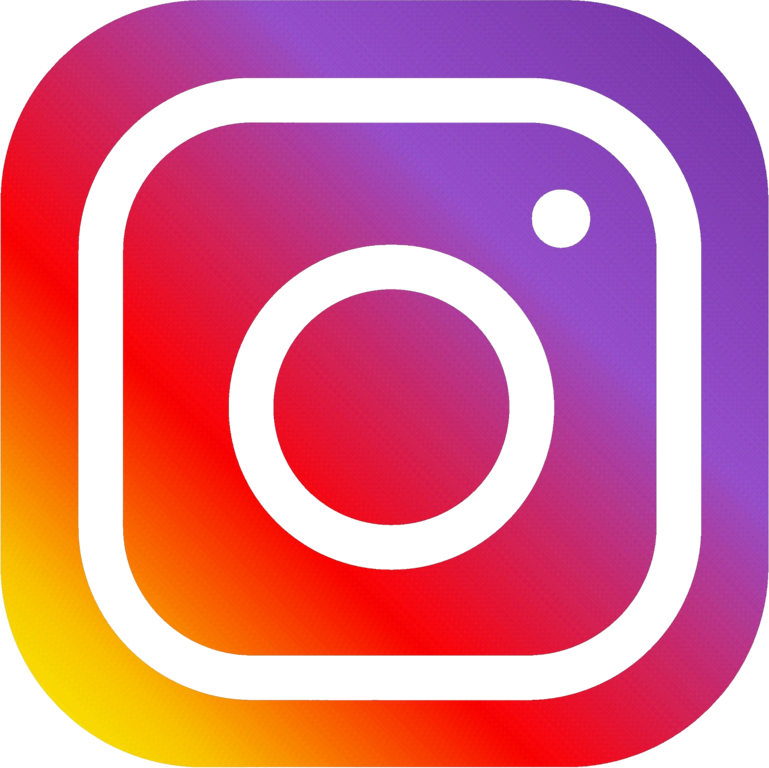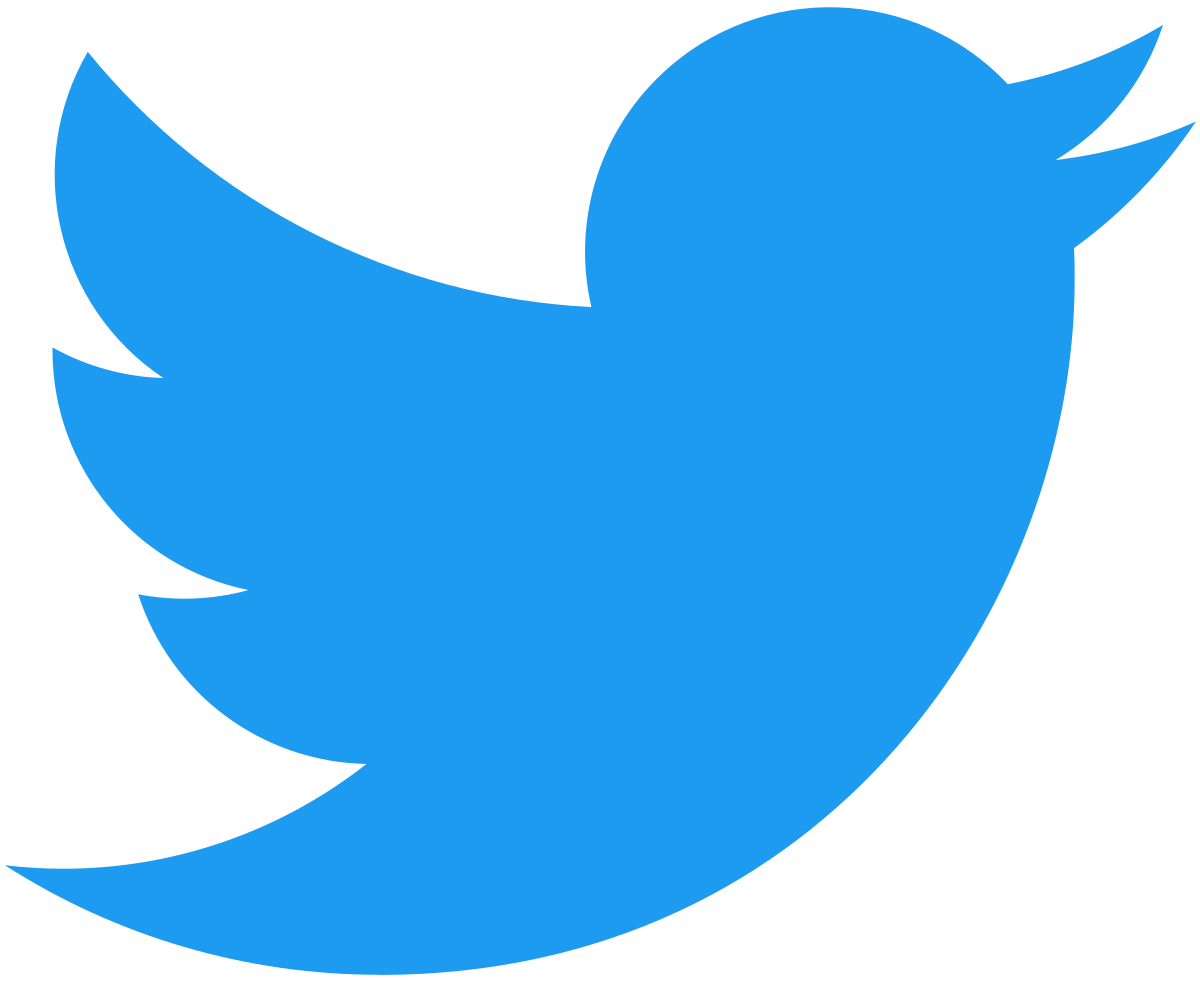黄金の門・チャーバハール:米がアジアでのインド伸長を恐れる理由
-

黄金の門・チャーバハール:米がアジアでのインド伸長を恐れる理由
インドは先日イランと、同国の戦略的港湾チャーバハールの開発・運営に関する10年間の協定に署名しました。インド政府は、中央アジア諸国およびアフガニスタンとの貿易を増大させ、さらにコーカサス、西アジア、東ヨーロッパといった新たな地域への道も開拓したいと考えています。
インドのソノワル港湾・海運・水路大臣はチャーバハールをめぐる自国とイランの協力について、「この港湾は、我が国をアフガニスタンや中央アジア諸国へ結びつける通商上の重要な経路になる」と述べています。
しかし、この両国の協定はこれまで、アメリカの制裁により風前の灯となっていました。
イランとインドは、2003年にこのプロジェクトをめぐる協議を開始していましたが、両国の関係発展に反対するアメリカの圧力により、そのあらゆる進展は実質的に妨げられてきました。しかし、2015年のイラン核合意を受けたアメリカの制裁緩和により、両国は協議再開に至りました。
チャーバハールはなぜ重要なのか?
インドは、6000億ドル規模の活発な産業を擁しており、西方の隣国と緊密な貿易を行うことを望んでいます。チャーバハール港を利用することは同国にとって、商品をまずイランへ輸送し、そこから鉄道・街道経由でアフガニスタンや資源が豊富な内陸国であるウズベキスタン、カザフスタンなどへ運ぶことを可能とします。インド政府関係者の一人は、この経路はロシアまでも到達すると語っています。
インド・デリーに拠点を置くシンクタンク「オブザーバー研究財団」のカビール・タネジャ研究員は、次のように述べています。
「インドにとってチャーバハール港は、西方や中央アジアでのさらなる投資機会を叶える、黄金の門だと言える」
チャーバハール港は現在、NSTC国際南北輸送回廊というプロジェクトを形成する重要なパーツとなっています。このプロジェクトの目標は、金融の中心地ムンバイをはじめとしたインドの主要都市と、アゼルバイジャンの首都バクーや中央アジア諸国の各首都とを、イラン経由でより安価かつより速くつなげることにあります。
アメリカの対インド制裁
アメリカはインドの核実験実施を受け、これまで1974年と1998年に2度、同国に制裁措置を取っています。
しかし冷戦終結後、アメリカはインドを味方に引き入れることに成功しました。そしてインドは、国連が承認していなくとも、ほとんどのケースでアメリカの圧力に従うことを余儀なくされました。
インドのこれまでにない伸長を恐れるアメリカ
インドは現在、世界で最も急速に経済成長を遂げる国の一つとなっています。同国は、その人口と地理的位置によって中国と同様、アメリカや西側から距離を置きつつ世界の主要な牽引役となれるだけの力を備えています。これこそ、一部の者がアメリカにとってインドが非常に恐ろしく感じられる理由だと考える点であり、そのためにアメリカは、インドが世界で独立した影響力を持つ道を閉ざそうと、あらゆる手段に訴えているのです。
アメリカの対イラン制裁は、これまでにもインドに大きな打撃を与え、長期的に見て同国の影響力増大を削いできました。また、アメリカによる制裁のリスクを回避すべくイラン産原油の購入を控えたことも、ライバルである中国と比べてインドを、原油供給国からの価格圧力に対しより脆弱にする原因となりました。
一部のアナリストは、もしアメリカがチャーバハール港の件について強硬な態度に出ようとするなら、それはこの「黄金の門」がインドに大きな飛躍の機会を提供しうることの証明になるだろうとしています。
アメリカは現在、中央アジアにおいて中国とロシアという2大勢力としのぎを削っており、同国にとっては、この地域の競争相手にインドも加わることは、好ましいことではありません。
前出のタンジャ氏は、「チャーバハールはより重要であり、インド政府はこの港を長期的に活気のあるものにするために努力したいと考えている」と述べています。
これについては、米ワシントンに本拠を置くシンクタンク「クインシー研究所(The Quincy Institute for Responsible Statecraft)」のグローバル・サウス・プログラム責任者であるサラン・シドレ氏も、「グローバル・サウスの国々は、自身の戦略目標に彼らを随伴させようとする米政府の望みにもかかわらず、自らの利益を追求し続けている。米政府は自国の諸政策が、グローバル・サウスを西側諸国から遠ざけ、さらに、米国の好機をこの広大な空間で随伴者がほぼない限られた状態とするような選択をこれらの国々に迫っていることについて、改めて考える必要がある」と述べています。