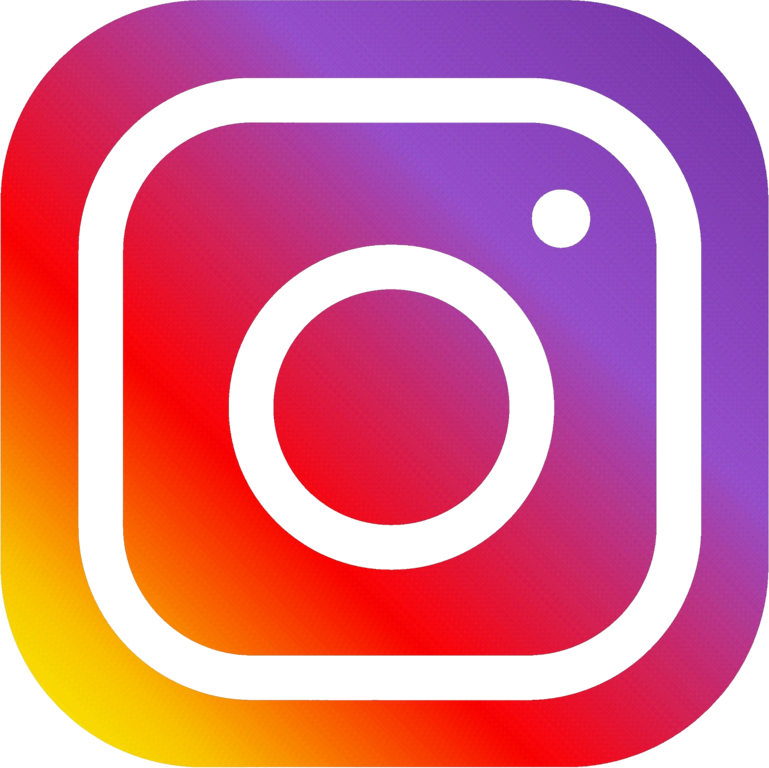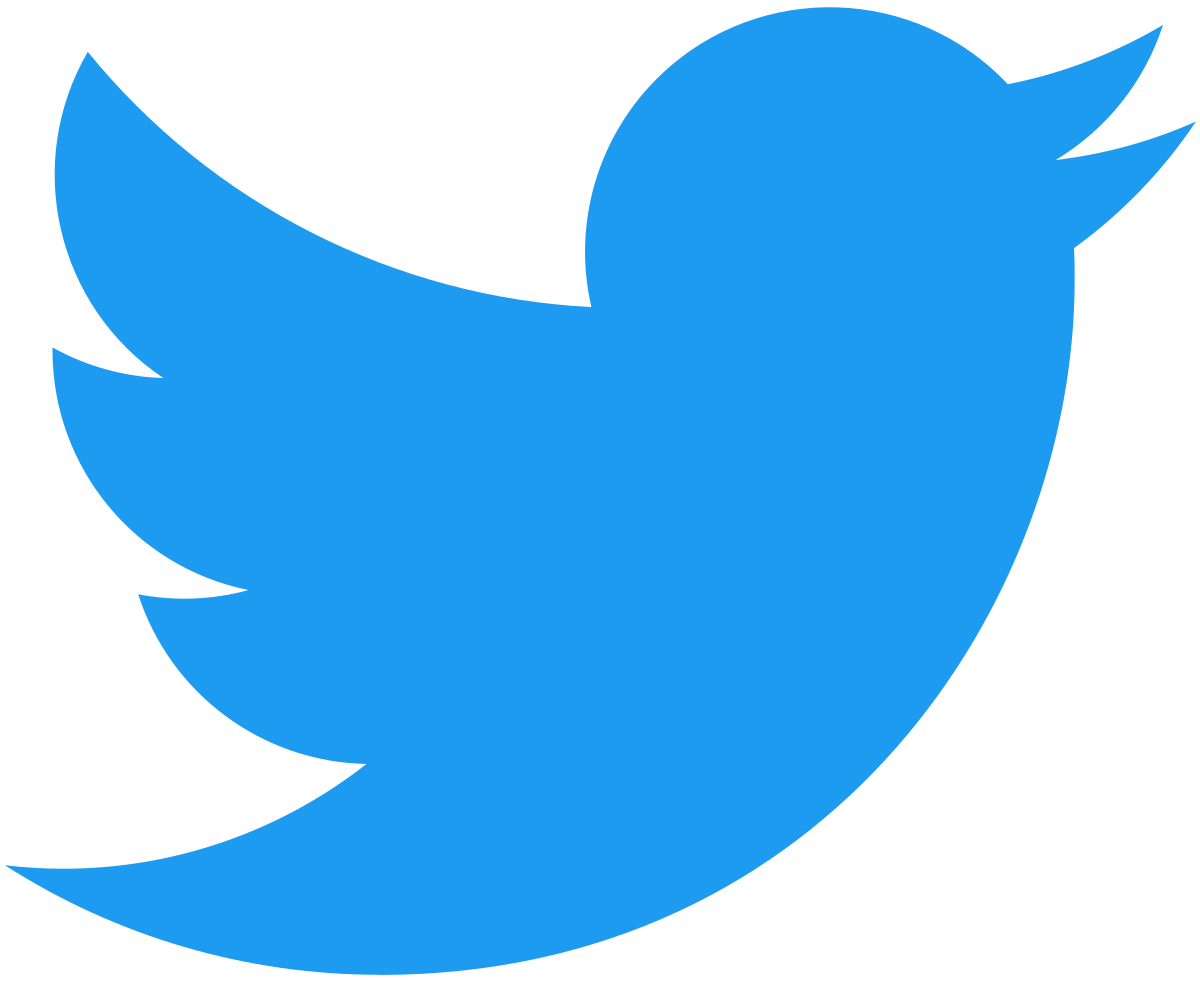米が中南米の緊迫化を扇動する目的とは?
-

米・ベネズエラ間の緊張が激化(右はトランプ米大統領、左はマドゥロ・ベネズエラ大統領)
アメリカがドナルド・トランプ大統領の再選に伴い、中南米で新たな政策を踏襲していることから、同地域の緊張が高まっています。
【ParsToday国際】トランプ米大統領がここ数週間、南米ベネズエラへの軍事的圧力を強め、アルゼンチンのハビエル・ミレイ政権に200億ドルの財政支援を提供し、パナマ運河における中国の影響力の遮断を画策していることから、中南米におけるアメリカの新たな目的をめぐり相次いで多数の分析がなされています。中南米におけるアメリカのこれらの行動の目的は地政学的影響力の維持に加え、中国やロシアといったライバル国への対抗、そして同地域における経済・安全保障上の利益の確保にあります。
この政策の主軸の一つは、ベネズエラなどの左派政権への圧力行使です。この点で、ベネズエラは再び権力誇示の舞台となっています。中米カリブ海への軍艦派遣および、ベネズエラのニコラス・マドゥロ政権に対する厳しい制裁の目的は、同政権を弱体化させ反体制派を支援することにあります。ここ数週間、トランプ大統領はカリブ海への軍艦派遣を通じて、ベネズエラに直接的な軍事的圧力を行使しようとしています。
しかし、こうした中で中南米へのアメリカの過去の介入経験からは、軍事行動が政治的安定につながりにくいことが判明しています。トランプ大統領は麻薬密売との戦いを名目に、誘導ミサイル駆逐艦、F-35戦闘機、原子力潜水艦、そして約6500人の兵士を含む広範な軍事装備をカリブ海に面したベネズエラ沿岸に派遣しました。また、カリブ海における米国の船舶攻撃により、少なくとも32人が死亡しています。
一方、トランプ政権の挑発的な行動により、南米コロンビアと米国の関係も緊迫化しており、双方の相互非難が激化しています。これに関して、トランプ米大統領がコロンビアのグスタボ・ペトロ大統領を「麻薬の売人」だとし、ペトロ大統領はトランプ氏「無礼で傲慢」と批判しました。トランプ大統領は19日日曜、自身のSNS「トゥルース・ソーシャル」において、ペトロ大統領をコロンビアで「非常に不人気の」人物で、かつ大規模な麻薬生産を奨励しているとし、「本日をもって、コロンビアへのすべての支払いと補助金は停止される」と表明しました。これに対しペトロ大統領もトランプ大統領の主張にSNSで反応し、「私はビジネスマンではなく、ましてや麻薬の売人などではない」と投稿しています。ペトロ大統領はさらに、トランプ大統領がコロンビアに対して「無礼で傲慢」であり、「自らの補佐官に騙されている」と付け加えました。
米国は予てから、対コカイン生産対策に協力していないとしてコロンビアを非難し、30年ぶりに同国を麻薬戦争非協力国リストに加えました。この措置を受けて、コロンビアは米国からの武器購入を停止しています。
同時に、トランプ政権は、パナマ運河に繋がる港湾や航路の管理への中国企業の関与を停止する合意を検討しています。このことが、重要なパナマ運河ルートにおける中国の影響力を制限する可能性がある一方で、中国はエクアドルからチリに至るまで、他の南米諸国への投資拡大により対抗する可能性が高くなっています。こうして、アメリカは西半球における中国との新たな地政学的競争に突入した格好となりました。この競争は、米国の台湾支援や中国との貿易戦争と相まって、米中間の冷戦につながる可能性があります。
中南米諸国はその戦略的な立地、豊富な天然資源、そして地理的に米国に近いことから、常にアメリカの外交政策における優先事項に掲げられてきました。近年、中国がパナマ運河などの主要インフラにおける影響力を増大させ、この地域の国々に大規模な投資を行っていることを受けて、米国は軍事、経済、外交的措置を通じてこの傾向を抑制しようと努めてきました。安全保障の観点から、米国は中南米諸国がライバル国、特に中国の軍事・諜報活動の拠点となることを懸念していると見られます。そのため、米国は軍事駐留の強化や安全保障協定の締結を通じて、この地域に対する覇権を維持しようとしているのです。
一方、トランプ政権は、中南米における親米派の大統領や政権を支援すべく、アルゼンチンのハビエル・ミレイ政権に200億ドルを融資しました。しかし、アメリカのこの行動はここ数週間で最も物議を醸した決定の一つとなっています。アルゼンチン政府への巨額の財政支援および同盟国との関係強化は、外国からの影響力に対抗する結束ブロックの構築というアメリカの戦略の一環となっています。アナリストらの見解では、この動きは経済的な同情からではなく、中南米における右派ポピュリストの勢力基盤の強化を目的に行われたということです。この決定が事実上、アメリカの納税者の犠牲の上に成り立っている一方で、その隠れた目的は、トランプ氏と同地域における思想面での彼の同盟者とのイデオロギー的連携を強化することにあります。
第2次トランプ政権の対中南米外交政策は、軍事的圧力、経済的影響力、そしてイデオロギー的同盟という3つの要素の組み合わせであると見られます。この組み合わせは、冷戦時代の地政学的野心を彷彿とさせると同時に、アメリカを中心とする新たな秩序体制の出現を示唆しています。しかし、新時代においては「ソフトパワー」が砲艦外交という枠組みでの露骨な権力誇示に取って代わられ、民主主義は主張される究極の目標ではなく、アメリカの利益に奉仕するための手段に過ぎないという点で異なっています。
総括すると、中南米における米国の目標は、ベネズエラのマドゥロ政権のような非同盟政権の打倒を試みることで地域覇権を維持すること、中国とロシアの影響力拡大の阻止、自らの同盟政権への支援、そして長期的な経済・安全保障上の利益の確保などとなっています。これらの行動は民主主義と発展というスローガンの下で行われているものの、実際にはモンロー主義の枠組みでの、米国の伝統的な裏庭としての中南米における権力定着化を目的としているのです。