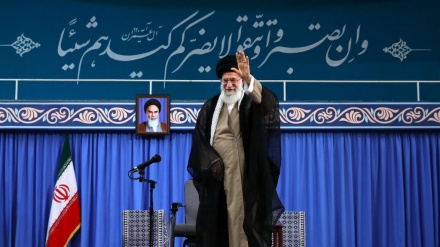大国としての中国の基準
中国は、現在、第3世界に属する国のひとつで、発展途上国として、ほかの国にとっての脅威ではないように見せていますが、アメリカはそう考えておらず、中国は世界の大国に変わるための大きな躍進を近いうちにとげ、まもなくアメリカの世界的な覇権を脅かすことになると見ています。アメリカのさまざまなシンクタンクも、中国はこれまでの大国としての基準に加え、新たな大国としての基準を有しており、影響力ある世界の大国に変わる可能性があるとしています。

人口は、これまでの大国としての基準のひとつでした。中国はおよそ14億人の人口を抱えており、有用な人材を持つ世界でもっとも人口の多い国です。また、近年、健全で能力ある社会の確立に大いに貢献する、識字率や労働の熟練度、公衆衛生のレベルの向上に成功しています。

また、国土の広さも、これまでの大国の基準のひとつです。中国は959万6千平方キロの面積を持つ東アジアの大国です。また、国土だけなく、広い領海を有しており、強力な海軍を持つ可能性が与えられています。

軍事力も、大国の基準のひとつです。中国は軍事力の点で世界3位となっており、その総兵力は228万5000人で、80万の予備役も有しています。一方で、兵器の技術の点では、中国軍はアメリカ軍に大いに差をつけられています。中国はある時期から、軍の構造改革のアプローチを、兵力から新型の兵器にシフトしています。中国の軍事問題を専門とする日本の研究者、小原凡司氏は、次のように語っています。
「中国の初の空母の開発は、軍事技術など、さまざまな分野における中国の発展の象徴である」

現在、中国は1300億ドルの軍事予算により、陸、海、空の各軍の大きな軍事的発展に向けた歩みを踏み出しています。この状況は、アメリカなどの西側諸国を懸念させています。中国の政治問題の専門家は、次のように述べています。
「中国の軍事力は、兵器による戦闘能力の改革の開始から、大変発展している」
経済力も、中国の大国としての基準のひとつとしてみなされています。第3世界に属する発展途上国だとしている中国は、その力を経済成長に依拠しています。中国は毎年、7%から8%の経済成長を遂げており、日本を抜いて、世界第2位の経済大国の地位を獲得しました。
中国は、今後20年間、世界第1位の経済大国となるだけでなく、貿易や投資などのさまざまな分野におけるアメリカの覇権に挑戦しようとしています。一部の有識者は、アメリカは中国周辺の危機をあおることで、中国に軍事予算を増大させ、経済成長を抑制しようとしていると見ています。
そのほかの大国としての基準に、さまざまな分野におけるテクノロジーが挙げられます。今日、軍事部門をはじめとするさまざまな分野でのテクノロジーは、中国の強大化の要因とされています。アメリカ空軍に所属していたアナリストのブライアン・ウィーデン氏は、次のように語っています。
「中国は、大変高い技術によって、衛星を打ち落とすことのできる兵器を保有した最初の国だ」
つまり、中国はこれまでの大国としての基準を有しており、また現代の大国としての基準を持つ国だということができます。これらの基準は、特にアメリカ政府関係者の間に、中国はアメリカの覇権にとっての深刻な脅威とみなされる、国際分野で主要国に変わりつつあるという見解を生みだしています。一方で、中国は大国としての能力に関して、弱点も持っています。

中国政府の重要な問題のひとつは、経済成長の低下であり、これにはさまざまな理由があります。汚職や業務の肥大化により、一部の中国資本は国外に持ち出されたりしています。中国の習近平国家主席は、人々の信頼を得るとともに、共産党の崩壊を防ぐため、汚職対策を共産党内部からはじめました。
また、品質の悪い製品の生産によって、中国は一部の市場を失っています。特に、インドなどの経済新興国が国際市場に進出したことで、国際市場での競争が激化しています。
このため、2017年の中国共産党大会では、習国家主席は改めて政府の優先事項を汚職対策と、生産状況の改善、経済成長の復活だと宣言しました。
中国政府は経済成長が続く中で、アメリカの妨害に直面しています。アメリカにおける一部の経済的、政治的な集団は、あらゆる手段によって、中国の経済成長を侵害することを強調しています。その一部は、中国を地域における軍拡競争に導くことにあります。アメリカの政治学の専門家は、このように語っています。
「アメリカは中国の経済成長に対抗することを決定している。それは一つの国だけが近い将来、世界経済のリーダーシップを得るようになるからだ。つまり、中国との経済戦争は、全面的なものだ。アメリカは全力でそれを行わなければならない。もしわれわれがこの分野で敗れ続けるならば、最終的に、今後10年で、アメリカはどのようにしても取り戻すことができないというところにまでいたる」
中国の政府関係者が国内問題により多くの注目を寄せることになった2つ目の要因は、社会格差です。北京大学の中国社会科学調査センターは、2014年の調査の中で、中国の1%の家庭は、中国全体の富の3分の1を所有しているとしています。また、4分の1の家庭は、国の富のわずか1%しか所有していない、ということです。
中国の輸出拡大に関して発表されている統計にもかかわらず、中国人の半数以上が、貧困の中で暮らしています。中国政府は常に優先事項の一つは貧困対策だとしています。中国の著名な経済専門家は、次のように述べています。
「中国の経済成長において、3つの事柄が影響を及ぼしている。国内外の投資、外国貿易、内需、これらは中国政府が、衰退しないよう、大変に留意している事柄だ」
中国の経済発展における3つ目の障害は、中国がエネルギー資源に極度に依存していることにあります。中国は60%以上のエネルギー需要を輸入でまかなっています。ペルシャ湾は最も重要な中国のエネルギー供給元とされています。アメリカとその同盟国が中東で作り出した危機により、中国への石油の移送が停止する可能性があります。それとともに、中国は鉄、銅などの輸入に依存しています。
また、食料に関しても、中国の食糧自給率は87%と高い数値を示していますが、2億人分の食料を外国からの輸入に頼っているといわれています。
国の主権や領土についても、中国は大きな問題に直面しています。台湾、チベット、新疆ウイグル自治区などがその問題の一部として挙げられます。中国は、インドとシッキムなどの領有権をめぐって対立しています。また、日本とは尖閣諸島をめぐる、東南アジア数カ国とは南シナ海をめぐる対立を抱えています。
中国における民族・宗派間の対立があらわになり、中央政府の力が弱体化することで、中国は分離の方向性に向かう可能性もあります。このため、中国が国際舞台で力を得ることに反対しているアメリカと一部のアメリカの同盟国は、中国を脅かしている民族問題を道具として利用する可能性があります
そのほか、中国が世界の大国としての役割を果たす上での問題のひとつは、イデオロギーと、国際的な文化の提示です。明らかに、中国は、大変な努力と秩序に基づいた力強い文化を持っており、これにより、世界第2位の経済大国の地位を得ました。しかし、西側のシステムに対して、中国は儒教をソフトウェアとして利用しています。儒教がほかの国の人々のニーズを満たすことができるのか、中国がこの方法によって世界的な地位を確立できるのかについては、疑問視されます。大国になろうとする国は、哲学を持っている必要があります。
また、中国は、日本やインドといった強力なライバルに直面しており、いずれも、アメリカの政策の下で、地域の秩序をアメリカの有利なように変えようとしている国です。
安倍首相が2020年までに改憲を行うと公約した日本の軍国主義的アプローチは、中国の軍事力に影響を及ぼすことができるほどのものです。これまで世界第2位の経済大国だった日本は、現在、国際的な政治情勢に影響を及ぼすためには、強力な軍隊が必要だという結論に達しています。中国の軍事問題を専門とする台湾国立政治大学のアーサー・ディング博士は、次のように語っています。
「中国の指導部は、いかなる軍事作戦を行う上でも、大変大きな注意を払わなければならない。日本は現在、アメリカとの安全保障協定に頼ることなく、よりよい軍備、訓練、設備を得ており、現在、中国と比べてよりよい環境にある」

アメリカのキッシンジャー元国務長官は、中国の世界的な地位を重視し、次のように語りました。
「われわれはアメリカと中国の2カ国のいずれの利益もひとつの方向性に見出さなければならない、類まれな時期にいる。冷戦後はこのような時代ではなかったし、2つの世界的大国が存在する時代は、二極的な冷戦時代から、より複雑な国際体制に変化した」