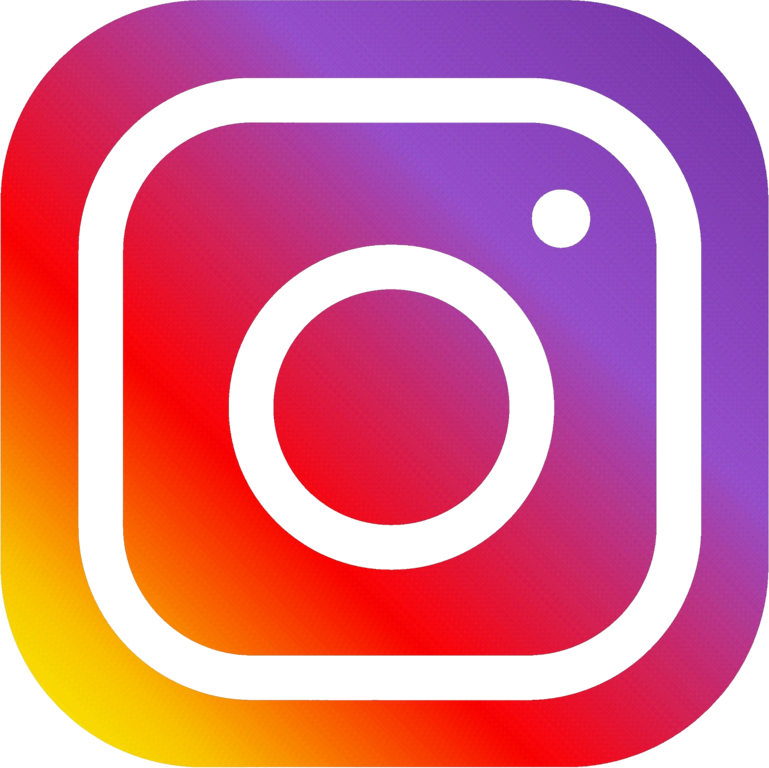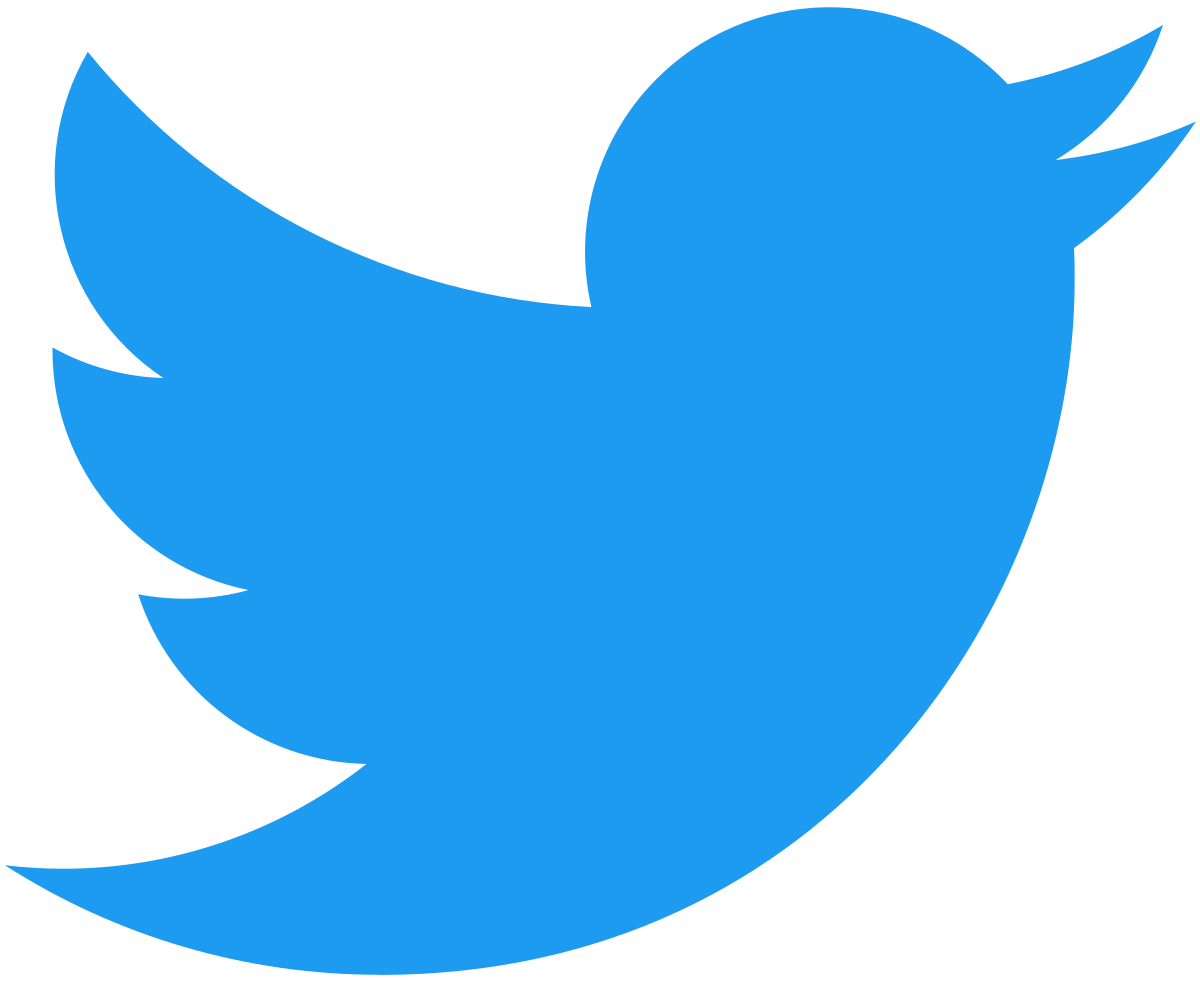普天間飛行場の隣の小学校、土壌のPFOSは通常の小学校の16倍
-

普天間飛行場の隣の小学校、土壌のPFOSは通常の小学校の16倍
沖縄県・普天間飛行場に隣接した小学校の土壌から、そうでない学校の16倍以上に相当するPFAS有機フッ素化合物が検出されたことが明らかになりました。

沖縄の地元紙・沖縄タイムスによりますと、沖縄県環境保全課は15日水曜、在沖米軍基地周辺など5地点で実施した土壌中の有機フッ素化合物PFAS(ピーファス)の調査結果を公表しました。
それによりますと、宜野湾市の普天間第二小で、対照地点(糸満市)より16・5倍のPFOS(ピーフォス)が検出されたということです。
その詳しい内容は、第二小では、土壌1グラム当たりPFOS6・6ナノグラムとPFOA(ピーフォア)0・7ナノグラムが検出されたのに対し、糸満市ではPFOS0・4ナノグラムとPFOA0・5ナノグラムだった、とのことです。
これについて、県は「基地の影響を受けている可能性を否定できない」と見解を示しました。
また、国内には土壌に関する基準値や分析方法が確立しておらず、県は安全性を評価できないということです。
一方、EPA米環境保護局は、住宅地域で健康被害をもたらす恐れがあり詳細な調査(スクリーニング)が必要とされる基準値をPFOS130ナノグラム、PFOA190ナノグラムと設定。地下水への汚染を防止するための基準値をPFOS0・038ナノグラム、PFOA0・92ナノグラムと定めています。
同基準値に照らすと、全地点で住宅地域では大きく下回った一方で、地下水への汚染防止では全地点で上回り、第二小のPFOSは最大の173倍という結果となりました。
これについて、京都大の原田浩二准教授(環境衛生学)は「土壌以外の環境への影響を考えると、決して安全と言える数値ではない」と指摘しました。
なお、調査は昨年12月、第二小を含む普天間飛行場周辺3地点、嘉手納基地周辺1地点、比較対照のため基地の影響がないとみられる糸満市で土壌を採取することで実施されています。