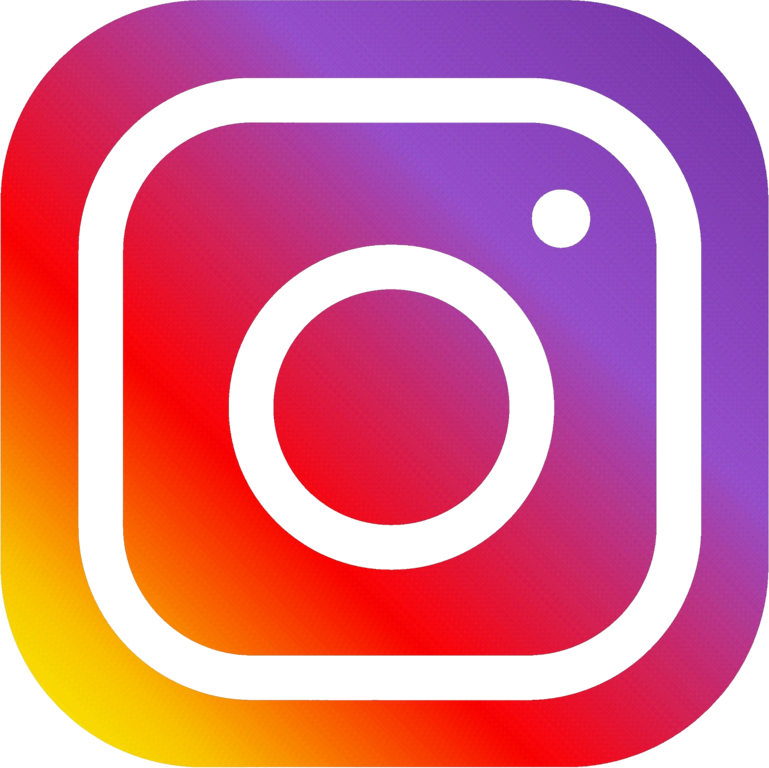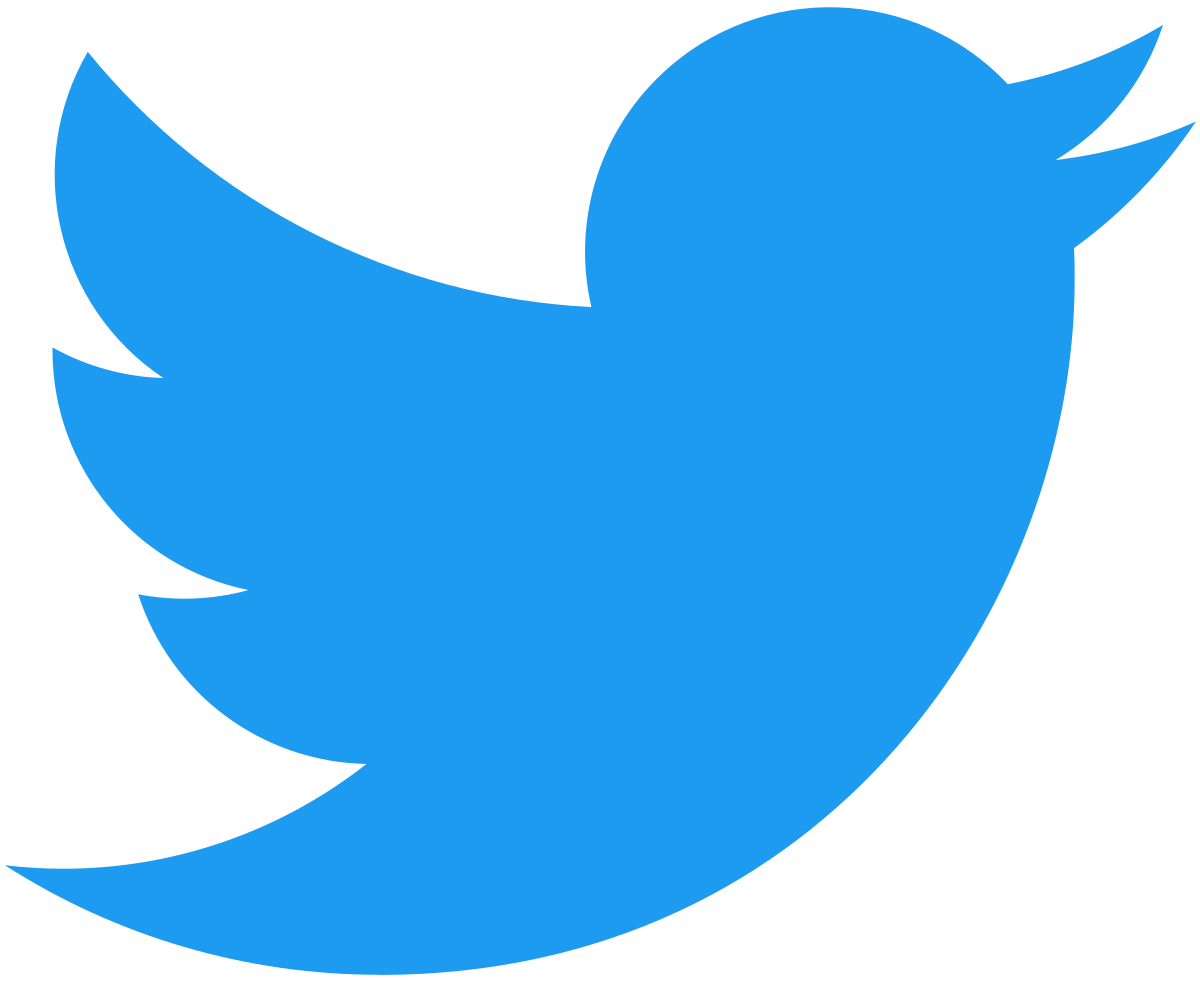インドが米国に屈服しないと強調した理由とは?
-

インドのピユシュ・ゴヤル商務大臣
インドが、米国に「屈服しない」と表明し、代わりに新たな市場の誘致に注力することを明らかにしました。
ゴヤル・インド商務大臣は同国首都ニューデリーで行われた建設業界イベントで、「もし誰かが望むなら、インドはいつでも彼らと自由貿易協定を結ぶ用意がある」と語っています。
また「インドは屈服することも、弱腰になることもない。我々は新たな市場を手に入れるだろう」と述べました。
【ParsToday国際】これらの発言が提起されたのは、米国政府がトランプ米大統領の命令により、先月27日以降はインドからの輸入品すべてに約50%の関税を賦課している中でのことで、しかもこの関税の半分はロシア産原油の購入に対する「罰則」だと発表されています。インドに対する新たな関税の全面実施は、貿易収支を超えた目的により通商政策を手段として用いることを意味しており、これにはロシアとエネルギー取引を行っている国への圧力行使も含まれます。インドからの輸入品に50%の関税を課すことで、米国は自らと広範な経済関係を持つ国に対して、最も厳しい関税措置の一つを課した形となっています。
この通商危機により、テクノロジーの活用と中国の世界的な影響力の抑制を基盤として築かれてきた、長年にわたる米印間の協力関係の強化は頓挫し、インドは経済安全保障のための貿易関係の多様化の検討を余儀なくされています。対インド関税の引き上げは、中国からインドへの生産移転を目指す米国の輸入業者の近年の戦略にも弊害を及ぼす可能性があります。
ドナルド・トランプ氏は、今年初めに大統領の座に復帰して以来、関税を広範な政治手段として利用し、世界貿易を混乱させてきました。トランプ大統領は長年にわたりインドの高い関税を「関税王」と称し、関税賦課と厳格な基準で自国内市場を守っているとしてインド政府を非難してきました。こうした問題は既に、オートバイやゴルフ用品など一部の米国製品の輸出に影響を及ぼしています。米印間の貿易交渉は今年に入って進展が鈍っており、インドへの支援は依然として神経を使う問題となっています。
インド政府は、2025年上半期に米国のエネルギー輸入を70%増の66億ドルとするなど、米国エネルギーおよび防衛装備品の購入増量によりアメリカの説得を試みたものの、トランプ大統領の追加関税決定を阻止することはできませんでした。
このように、トランプ大統領が課した最近の一連の関税措置は、インド政府がこれらの関税を不公平、不当、かつ非論理的と見なしていることから、米印関係を緊張させた格好となっています。この点に関して、トランプ大統領は米・インド間の関係悪化を理由に、インドで開催予定だった「クアッド(日本、米国、オーストラリア、インドの4カ国で安全保障や経済を協議する枠組み)」安全保障対話の次回会合への参加を取りやめにしており、これは米印関係の緊迫ぶりを示すもう一つの兆候といえます。
同時に、関税を盾にしたアメリカの圧力行使(特にインドのロシア産原油購入を妨害)の影響を受けた形で、インドと中国は先週、関係修復の兆しを見せました。先だって中国・天津で行われたSCO上海協力機構首脳会合の傍ら、インドのナレンドラ・モディ首相と中国の習近平国家主席を含む国境協議や二国間会談が行われ、両国の指導者は国境紛争の解決および正常な通商の復活をめぐり合意しています。また、インドと中国間の空路直行便の再開は、両国の経済と貿易に広範な影響を及ぼすと考えられます。貿易業者、投資家、観光客の移動の円滑化により、中国とインドの間の貿易の活性化、共同投資の増加、そして経済協力の発展につながる可能性があります。中国・インド間の関係改善は、米国の圧力に対する戦略的な対応と捉えることができます。
南アジアを専門とするアメリカの外交政策作家マイケル・クーゲルマン(Michael Kugelman)氏は、「米国に対するインドの信頼は崩壊しており、米国当局は自らが与えた損害の深刻さを未だに認識していない」と指摘する。こうした状況の下、中国は2日間にわたるSCO上海協力機構サミットの開催によって、独自の立場を獲得した形となりました。
クーゲルマン氏によれば、モディ・インド首相の中国・北京訪問は、中印関係が改善し、印米関係が悪化している最中のことであり、この対立は、強力かつ象徴的なイメージを生み出すだろうと思われます。