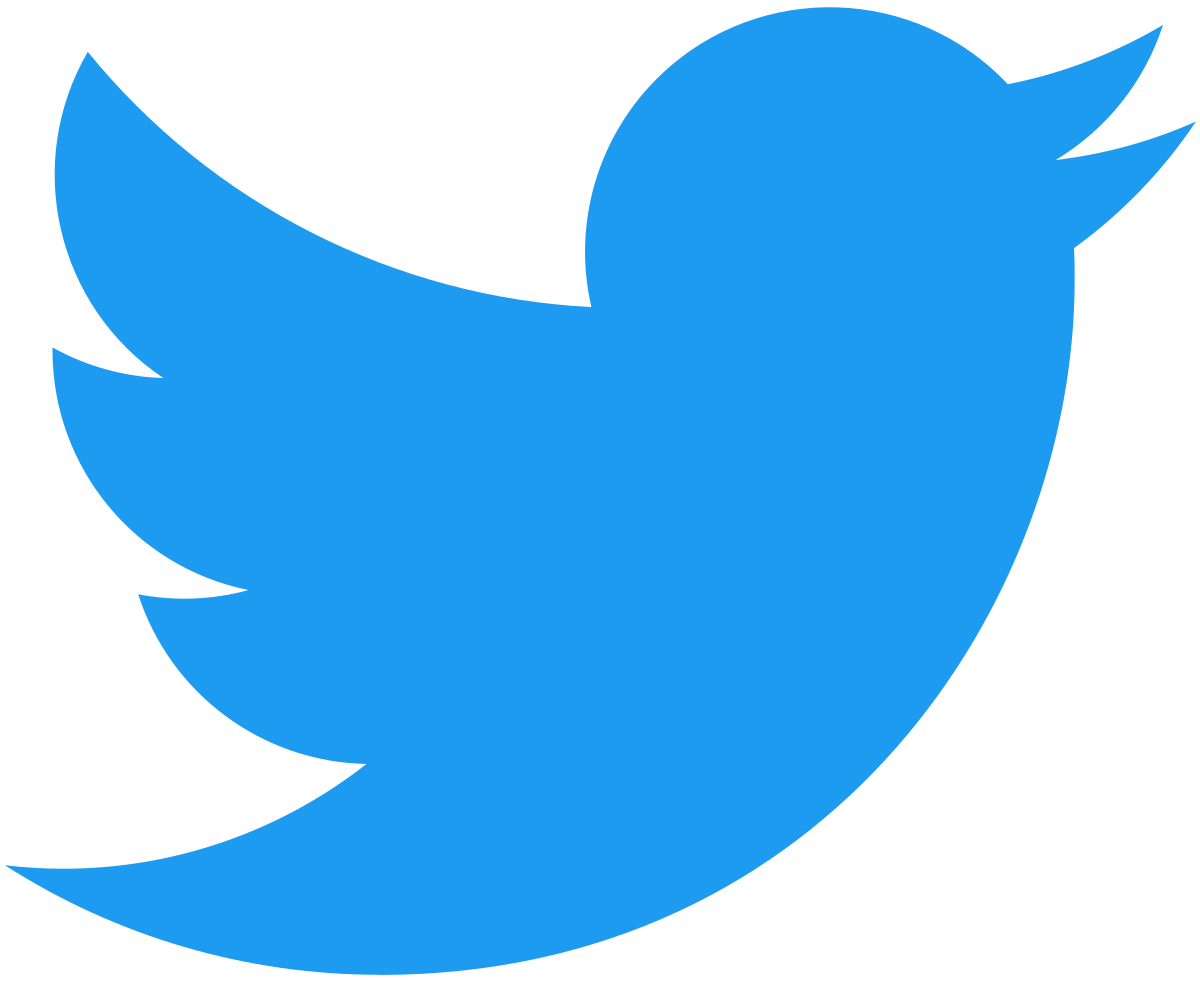ハリウッドによる戦争扇動 米国の介入主義の推進力
-

ハリウッドによる戦争扇動 米国の介入主義の推進力
アメリカの映画産業は2001年の同時多発テロ以降、それまでの戦略と併せて新たな戦略をとるようになりました。しかしそれは、イスラムに対する憎悪・恐怖感を掻き立てるものでしかありませんでした。
9.11以前、アメリカの敵は「他者」として遠くから影響を及ぼしてきました。第二次大戦では敵は都市を破壊し、冷戦下では都市を2つに分断しました。しかし、それらはいずれもアメリカから遠く離れた土地での出来事でした。ハリウッド映画ではそうした出来事がおどろおどろしく描かれてきましたが、それでも遠く離れていることがアメリカの安全を保証していました。しかし、9.11はアメリカ本土も攻撃対象となることを証明し、アメリカがさらなる安全保障・軍事措置をとる下地を整えることになりました。
そしてこの時、9.11以前に使われたあらゆる言説が総動員され、「テロとの戦い」というスローガンに集約されました。第二次大戦中の「世界で役割を果たす」という言説、冷戦下の諜報的な言説、冷戦後の最終戦争的な言説などがそうです。
そして、自己と他者を分けるイデオロギーが採用され、「我々」と「彼ら」という代名詞が頻繁に使用されるようになりました。
「テロとの戦い」という言説が「犠牲」「テロリスト」「英雄」という3つのキーワードから成り立っていると考えると、そこに上記で触れた過去の3つの言説の痕跡があるのを見て取ることができます。
「世界で役割を果たす」という言説は「犠牲」、諜報的言説は「テロリスト」、そして最終戦争的言説は「英雄」としてハリウッド映画に描かれています。では、ハリウッド映画はどのようにしてこうしたイデオロギーを動員し、「テロとの戦い」という言説の信頼性を高めることができたのでしょうか?
1.「犠牲」の演出
9.11が語られる上で重要なのが、「犠牲」と「痛み」の強調です。そこでは、犠牲者の痛みと遺族の痛みが強く訴えられました。こうした個人的な痛みを人々の痛みとして一般化し、国家的な追悼を醸成する必要が生じたのです。
特に、犠牲者遺族などの証言は痛みを一般化する上でメディアで大いに用いられた手法でした。そうすることで誰もが犠牲者になれたのです。2011年の映画「ものすごくうるさくて、ありえないほど近い」(スティーヴン・ダルドリー監督)は、見る者に9.11直後の日々を思い起こさせ、当時のように団結を意識させます。
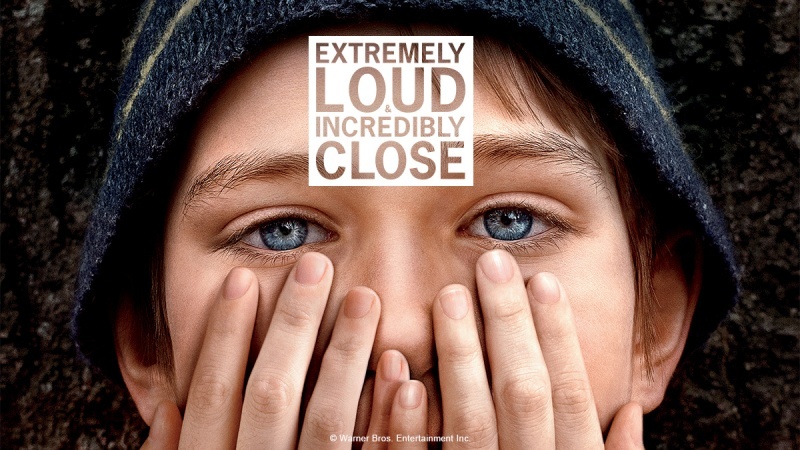
2.「敵」の演出
9.11後のハリウッド映画は、アメリカが遭遇する「他者」を「アラブ人/イスラム教徒」として描くようになりました。「ワールド・オブ・ライズ」(2008年)「チャーリー・ウィルソンズ・ウォー」(2007年)「レンディション」(2007年)「オーシャン・オブ・ファイヤー」(2004年)「シリアナ」(2005年)「アイアンマン」(2008年)といった作品ではいずれも、「アラブ人」や「イスラム教徒」とされるキャラクターがアメリカやアメリカ人に対してテロを仕掛けるように描かれています。現実世界では、平和に暮らすムスリムが暴力的なムスリムよりも圧倒的に多いにもかかわらずです。
3.「英雄」の演出
9.11後の映画に登場する「英雄」は、超人的な力を持った不屈のヒーローではなく、明確なイデオロギーを伝える象徴であれば十分です。そのイデオロギーとは「復讐」と「国家への犠牲」です。2011年の米軍によるオサマ・ビンラディン殺害の過程を描いた「ゼロ・ダーク・サーティ」(キャスリン・ビグロー監督)では、主人公はごく普通の女性ですが、復讐心に燃えた愛国心の強い人物です。
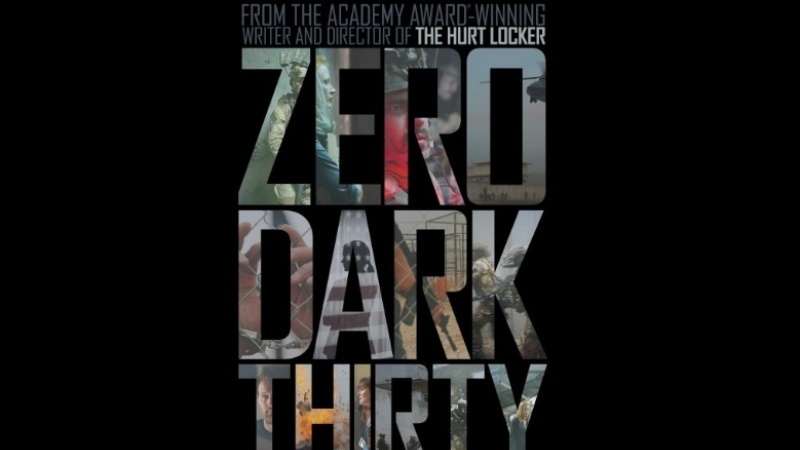
これら3つの要素により、9.11後のアメリカの言説は完成しました。アラブ人やイスラム教徒をテロリストとして描き、「テロとの戦い」という言説を生み出し、イスラム憎悪を拡散させたのです。そしてそれが、アメリカや西側諸国の好戦主義、拡大・介入主義を正当化しているのです。