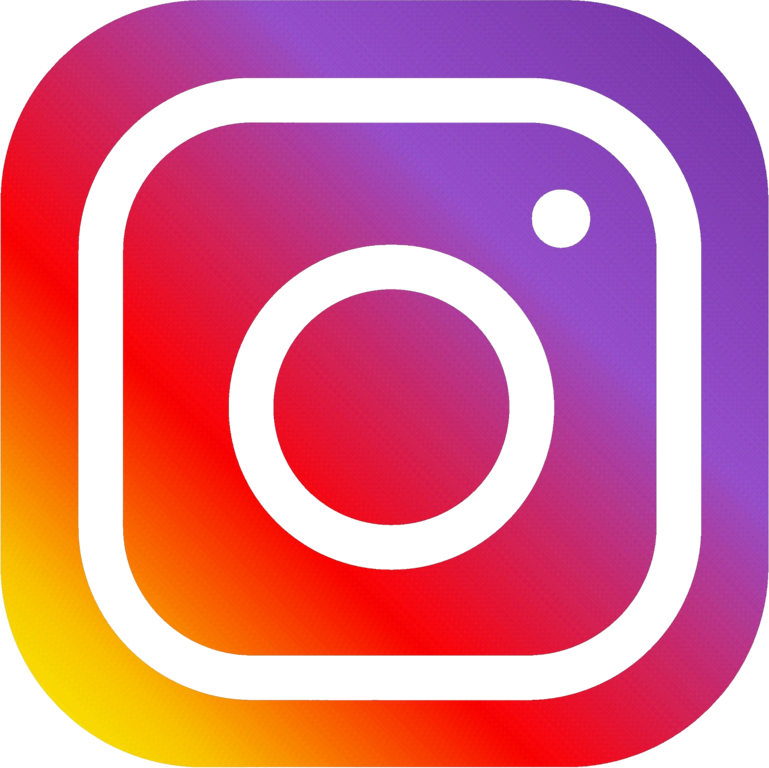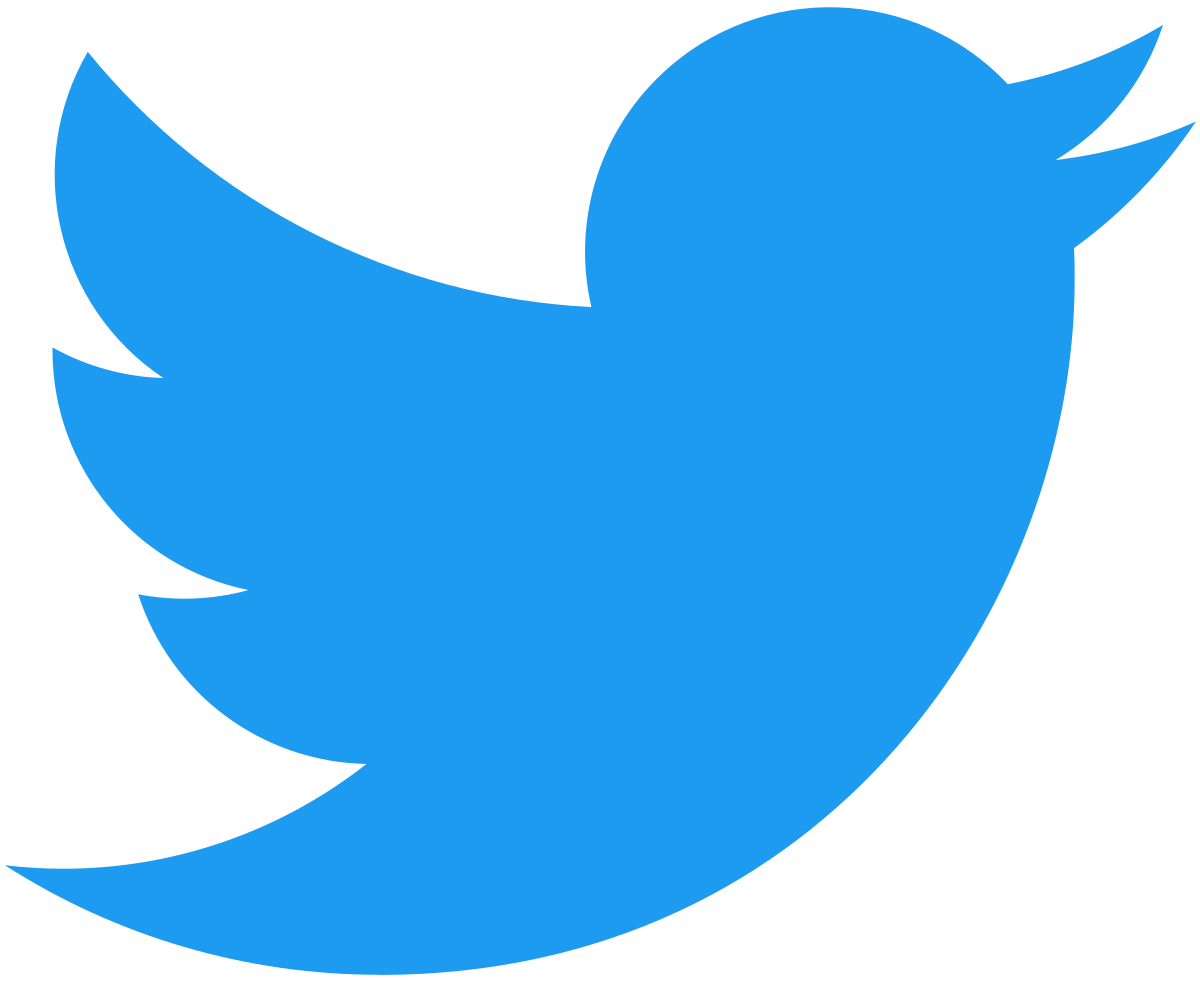戦略的対決の寸前にある米中;経済競争から新たな勢力軸の形成へ
-

戦術的合意から戦略的反目へ:米中間の「冷戦」が引き起こした結果
最近の情勢変化からは、アメリカと中国の関係が今や戦略的競争のレベルを超え、多くのアナリストが「新冷戦」と称する段階に達したことが見て取れます。これは20世紀の例とは異なり、より広範な経済的、技術的、地政学的側面を持つとともに、すべての国際的勢力を巻き込んだ紛争といえるものです。
カタール国営衛星通信アルジャジーラは、米中関係の最近の動向を検証したある報道において、「米中という両大国間の緊張はもはや従来の世界大国間の競争という枠組みでは解釈しきれず、『新たな冷戦』と言えるレベルに達している」と報じました。
【ParsToday国際】メフル通信によりますと、中国は長年にわたり、同国における改革の立役者・鄧小平氏の指針に基づき直接衝突を回避してきたものの、現在ではその経済力と技術力に依拠して国際体制における主導的地位を確立しようとしています。
この報道では、アメリカによる新たな国際大国の分類を論拠とし、米国は中国をライバルではなく「主要な脅威」と見ているとされています。この変化は、冷戦期のソ連とは異なり中国経済が今や米国経済と同等の水準に達し、購買力平価で米国を凌駕していることによるものです。そのため、米中間の軍事的あるいは経済的対立はどのようなものであれ、世界的な影響を引き起こしかねません。
アルジャジーラによれば、中国は決定的な衝突を先延ばしにしようと努力しており、その理由として時勢が中国の有利になるよう進行中であること、輸出の増加、世界の工業生産に占める30%のシェア、前例のないペースでの軍事力開発により中国が勢力を増大する存在にのし上がっていることが挙げられています。
一方、新興・先進産業に必要な希土類元素の80%以上を支配している中国は、経済的圧力行使のための重要な手段を有しています。アメリカ化は直接的な競争に加え、地政学的な動向にも懸念を募らせています。一部のアナリストの見解では、中国とインドの関係修復と中露協力の拡大は、世界の勢力均衡を変革しうる「三国間軸」の形成を示唆するものだと見られています。第1次ドナルド・トランプ政権で大統領補佐官(国家安全保障担当)を務め、その後トランプ大統領を強く批判するようになったジョン・ボルトン氏(76)をはじめとする著名人は、こうした傾向を「21世紀のアメリカ戦略に対する前例のない脅威」と評しています。
これとは対照的に、アメリカはサイバー活動、経済スパイ活動、そして西側諸国の産業における中国の影響力拡大といった疑惑を提起することで、米国民と自らの同盟国に対し、中国の台頭がもたらす危険性を認識させようとしています。しかし、経済的な相互依存関係とグローバル供給網が極めて広範囲であることから、米国は中国完封政策を実行できていません。
これらの傾向を総合的に捉えると、中国と米国の競争は拡大し続けており、前回の冷戦とは異なり世界各国にとってその影響の回避はほぼ不可能であることが分かります。またその理由として、世界経済が米中という両大国と複雑に絡み合っており、この両国の関係の変化が貿易や安全保障、国際体制・秩序に直接影響を及ぼすことが指摘されます。