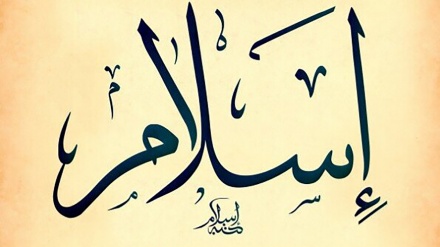神の公正(3)
今週も神の属性の一つである、神の公正についてお話しすることにいたしましょう。
今回の番組では、自然界の災害がもたらす結果に注目することで生命の世界の公正さと英知を明示し、イスラムを学んでいきましょう。
前回の番組では、自然災害についてお話し、世界が公正や英知に基づいて構成されているのであれば、なぜ世界のあちこちで台風や洪水、地震といった自然災害が起こり、多くの人の命や財産を奪うのか?といった問いを提示しました。こうした出来事に注目し、生命の世界の公正の問題はどのように説明されるのでしょうか。
災害など好ましからざる出来事がどんなに破壊的で不快なものであるとしても、私たちの受けた利益や被害が判断の基準になるべきではありません。このような自然現象に関して、それらの影響を全体的に考慮し、より正確な理解を得るべきでしょう。今夜の番組ではこれについてお話することにいたしましょう。
お話ししたように、より正確に世界の出来事を眺めてみると、これらの中で私たちにとって害をもたらすものが、現在であれ、未来であれ、他者には利益になることだったりします。概して世界の動きは定められた目的を実現するためのものですが、この道において人は被害を受けたり、災難に巻き込まれる可能性があるのです。これに関してイスラム教徒の思想家で、研究者のムーサヴィーラーリー師はこのように語っています。
「もし世界の秘密を知ることができるなら、様々な出来事がもたらす結果は私たちにとって明らかになるだろう。現在の出来事は、それまでの一連の要因が生み出したものであることは明らかであり、それ自体将来他の出来事の要因となる。もし私たちがより高い地点から世界を眺め、世界の秘密を直接目にし、過去や未来、一連の生命の世界の出来事の結果を評価することができたなら、生命の世界を占める関係が公正なものであることがわかるだろう。こうした秘密が明らかになっていない今、性急で一方的な先入観を持つのはやめるべきだろう。どれほど自然が特別な目的を実現する実行者であるか、通常の流れで人間がそれを考えるのは難しい」
好ましからざる出来事に関する判断は、突然町に入ってきて、強力なブルドーザーで通りの建物を破壊する人を判断するのに似ています。最初はこの行為は不条理な破壊と見なされますが、よく見てみると、この破壊は最高の技術的な原則に基づいて住宅地を建設しようとしている前段階かもしれません。その場合、こうした行為は抗議されるのではなく、賞賛されるべきものでしょう。
専門家によれば、災害は一見すると好ましい者ではありませんが、人間を啓蒙する要因となりうります。好ましからざる災難を深く見つめることで、人間にもたらされた災難の中心に恩恵、あるいは貴重な教訓が隠されていることが分かるでしょう。言い換えれば、災害は警報のようなものであり、人間を自らの欠陥の認識やその改善に向かわせるものです。
争いや衝突は、進化の途上と言えるでしょう。実際、人間やその他の生き物の成長や進化の道は困難や不穏の間にあります。つまり、困難は人間個人の成長や進化に大きな役割を負っています。金属は釜の中で溶解されなければ、精製されません。人間もまた困難や災難に苦しまない限り、精神は鍛えられず、成長も遂げません。困難は人間の意志や決意を強くし、自己形成において効果的な役割を果たしています。
神を求める、友好、寛容、献身といった人間の美徳の表れは、困難に打ち勝つ努力の中でのみ実現されます。シーア派初代イマーム、アリーは、困難の中で育った人を乾燥した砂漠の中で成長する木になぞらえています。それらは強風や嵐にも耐えうる強い幹を持っています。一方で、楽なことを求める人を川辺で常に水を得ることのできる木々になぞらえています。それらは皮も薄く、風に対しても抵抗力が弱く、もろい存在です。制限のない享楽をもとめることは、人間を意志のない弱い存在にします。日々の浮き沈みを味わわず、甘やかされて育った人、または人生の中で困難を経験しなかった人は、耐久力がなく、不運な人たちなのです。
実際、生命の世界において善と悪、困難と楽、病気と健康、破壊と繁栄は隣り合っています。この世界は、人間が楽をして楽しむために創造されたのではなく、楽しいことも苦しいことも共にあります。この世界で、すべての人間は様々なレベルで、それぞれの困難に直面します。人間はこの世界において、絶対的な幸福には到達せず、原則的にその創造の目的はそのようなものではありません。イランの哲学者で思想家のモタッハリー師は、「神の公正」という著書の中で、人生において苦しみが存在する理由についてこのように記しています。
「世界は一連の対立である。存在物と非存在物、生と死、存続と消滅、健康と病気、老いと若さ、そして幸福と不運がこの世界には共存している」
興味深い点は、痛ましい出来事に関して人間はそれらをのちの勝利や成功のための前段階として利用することができるということです。かつて何度となく、コレラやペストといった伝染病が多くの人間の命を奪い、これらは人間にとって一種の敗北とみなされていました。こうした中、これらの病気によって人々が亡くなったことで、研究者らは病気を確実に根絶しようとしました。最終的に彼らは病原菌やウイルスの役割を突き止めました。彼らはこうした重要な発見により、様々な実験を通して、病気の予防方法を解明しました。こうして多くの病気から人間を救うことができるようになったのです。
このことから、災難はコインの表と裏のようなものだということができるでしょう、一方には苦しみと悲痛があり、他方には問題を乗り越え、解決策を見出すための人間の努力があるのです。つまり人間の科学的な成果や様々な分野での成功は、こうした災難が生み出したものであり、人間の失敗や不足のおかげなのです。イスラム教でも災難や問題を乗り越える重要性が説かれています。コーラン第94章アッシャルフ章、胸を広げる、第5節から6節には次のようにあります。
「あらゆる難しさと共に楽さ(安楽)がある。明らかにあらゆる困難と共に容易さがあるのである」
この節を少し注意深く見てみると、コーランが困難の後に楽があるのではなく、困難と共に楽があると強調していることがわかります。モタッハリー師はこの節について、このように解釈しています。「災難や困難の中には幸福が隠れている。ときに幸運の中に不運が創造されているように、これがこの世界の成り立ちなのだ」
さらにこのように述べています。「恩恵が恩恵になるか、災難が災難になるかは、それに対する我々の反応次第である」
このように恩恵もまたプラスとマイナスの影響があり、これは人間の計画にかかっています。例えば雨と川は人間にとって恩恵あるものです。人間が川にダムを作れば、それを農業や飲料水、水力発電に使うことができます。しかしこの自然の恩恵を利用するために計画を持たなければ、あるいはそれを正しく使用しなければ、川が氾濫し、洪水が発生した時にこの恩恵は破壊的なものとなり、畑や村を押し流し、人間の命さえ奪ってしまうでしょう。
このことから、一見すると好ましくない出来事が世界の公正の原則を傷つけると考えてはなりません。すべての現象は至高なる計画や意志、思想から発生しています。知性あるすべての人間は世界のこうしたすべての措置を目にすることで、世界は目的を持った集合体で、完成に向かっており、あらゆる現象は明らかな基準に従っているということを理解するのです。それゆえ自然界の危険な出来事は、創造の欠陥、神の公正さに反するものではないのです。