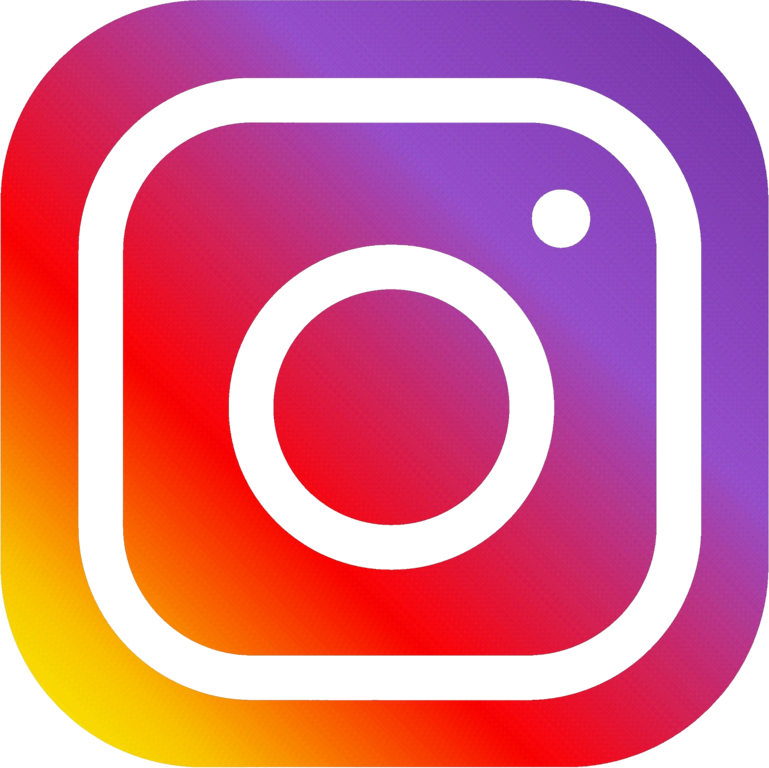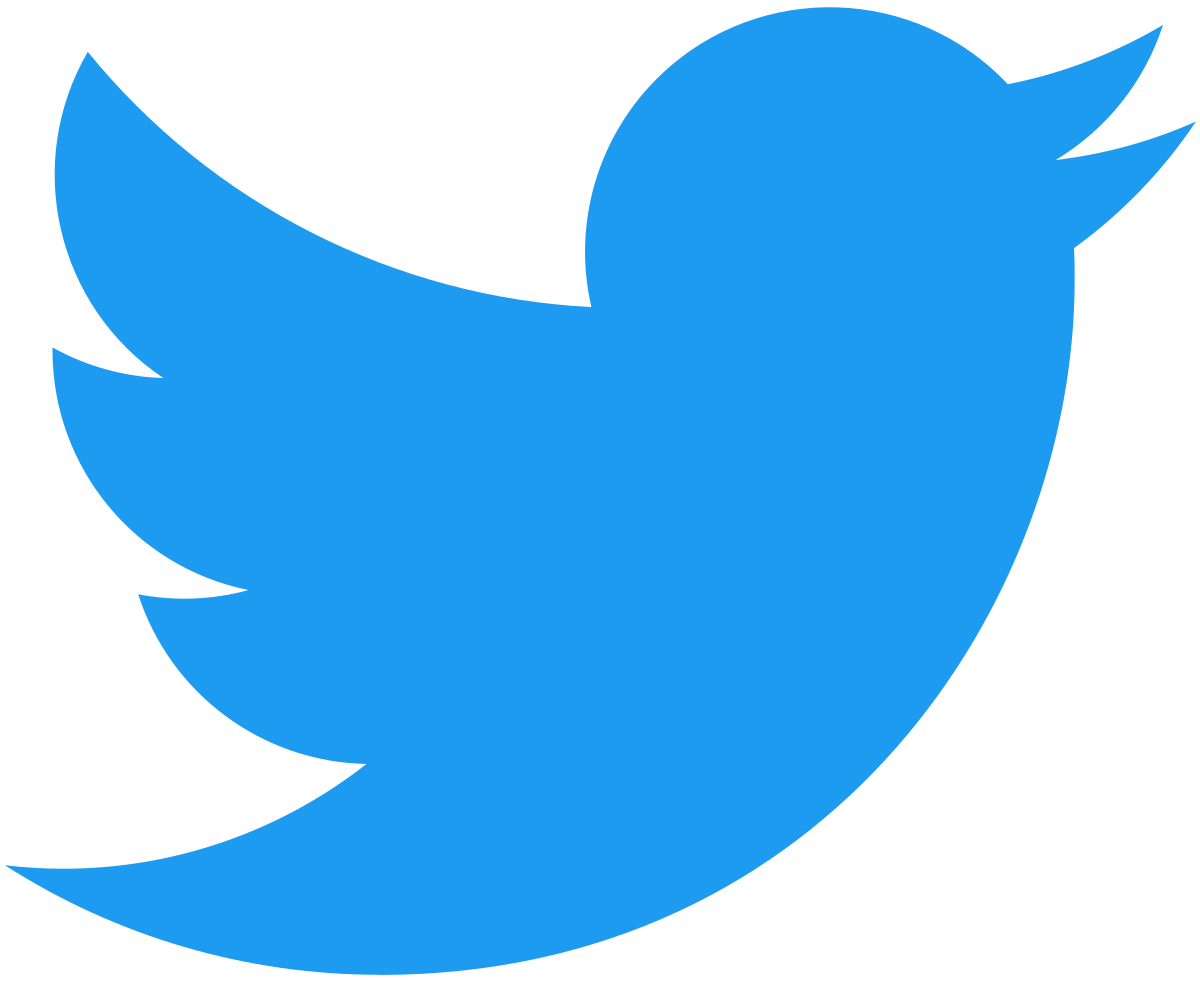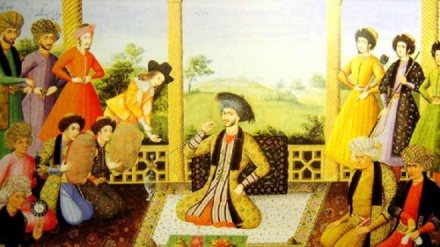ペルシャ語ことわざ散歩(184)「支配者が切断する手には流血もなく科料もない」
皆様こんにちは。シリーズでお届けしております「ペルシャ語ことわざ散歩」、今回は「支配者が切断する手には流血もなく科料もない」ということわざをご紹介してまいりましょう。
ペルシャ語での読み方は、Dastii raa ke Haakem bebore, khuun nadaare yaa diiye nadaareとなります。
おそらく、皆様はもうこのことわざの本来の意味をご想像いただけたかもしれませんね。
この表現は、「支配者が誰かの手を切断するのは、その人物がそうされるべき重大な罪を犯したことが理由であり,正当な行動の実施であること」、そして「もしもただの人が誰かの手を切断したならば、それは重大な犯罪であり罰せられるべきである」ということを意味しています。
つまり、裁判官や判事などが罪人にしかるべき処罰を科すこと、また犯罪者がその引き起こした犯罪にそってしかるべき懲罰を受けることは当然であり、その処罰を命じた人が科料や罰金を払う必要はない、ということになります。
これについては、紀元前18世紀の古代メソポタミアのハムラビ法典に出てくる「目には目を、歯には歯を」という表現がよく知られているかと思います。
もっとも、逆に裁判官が誤った裁断を下したり、みだりに報復刑を命じた場合にはその裁判官が有罪となり、罰金を支払わなければならないそうです。
ちなみに、1901年にはイラン南部スーサにおきまして、フランスの考古学者により高さ2.25mの石棒に楔形文字で刻まれたハムラビ法典が発見されています。
これにちなんで調べてみましたところ、同害を与えることによる報復は、古代における粗野で野蛮な刑罰とされてきましたが、「倍返しのような過剰な報復を禁じ、同等の懲罰にとどめて報復合戦の拡大を防ぐ」、すなわち、予め犯罪に対応する刑罰の限界を定めることがこの条文の本来の趣旨であり、刑法学においても近代刑法への歴史的に重要な規定とされている」ということです。
イランに紀元前の時代から、このように体系化された刑法が存在していたということは実に驚くべきことだと思われます。
今回は、古代イランの歴史にも関係していると思われることわざをご紹介しました。それではまた。
この番組は、IRIBイランイスラム共和国国際日本語通信パールストゥデイよりお送りしています。