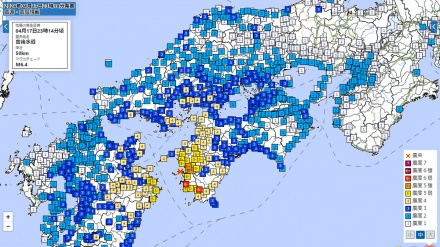沖縄周辺で今なお大量の軽石が漂流、漁業や観光業への影響を懸念
-

沖縄周辺で今なお大量の軽石が漂流
小笠原諸島の海底火山の噴火により、沖縄本島周辺には今なお大量の軽石が漂流し、漁業や観光業への影響が懸念されています。
NHKによりますと、 同局のヘリコプターで25日月曜に撮影した映像からは、大量の軽石が沖縄本島北部の沖合を中心に漂流している様子が確認され、漁業や観光業への影響が懸念されています。
小笠原諸島の海底火山・福徳岡ノ場で去る8月に発生した噴火ににより、大量の軽石が噴出し、沖縄県と鹿児島県の奄美地方などに大量に漂着しています。
このうち、沖縄県名護市の屋我地島や大宜味村、国頭村では軽石が沖合に幾重にも帯状に漂い、一部は海岸に積もっていたほか、今帰仁村や本部町の海岸にも軽石が漂着していました。
特に国頭村の辺土名漁港の内側には大量の軽石が流れ込み、漁船を陸に揚げる漁港のスロープでは重機による軽石の除去作業が続けられていました。
同村の漁港の生けすには、大量の軽石が入り込んだことによりサバの仲間200匹余りが死んでいるのが見つかり、魚の体の中から細かい軽石が見つかったということです。組合は、魚がエサと間違えて軽石を飲み込んだのが原因とみられるとしています。地元の漁協は魚が細かい軽石をエサと間違えて飲み込んだのが原因と見られるとしています。
これについて、国頭漁業協同組合の村田佳久組合長は「漁港に押し寄せる軽石のせいですでに1週間ぐらい漁に出ることができず、大変な状態になっているが、生けすの魚も出荷できなくなった。この状況がいつまで続くか心配だ」とコメントしました。
沖縄県は、漁港や海岸に漂着している大量の軽石について、現場に職員を派遣するなどして状況の把握を進めているほか、処理方法についても、海岸に流れ着いたゴミなどの処理の際に活用できる国の補助金制度の利用の可否を国に照会するとともに、市町村とも連携して検討していくことにしています。
ラジオ日本語のユーチューブなどのソーシャルメディアもご覧ください。
https://twitter.com/parstodayj