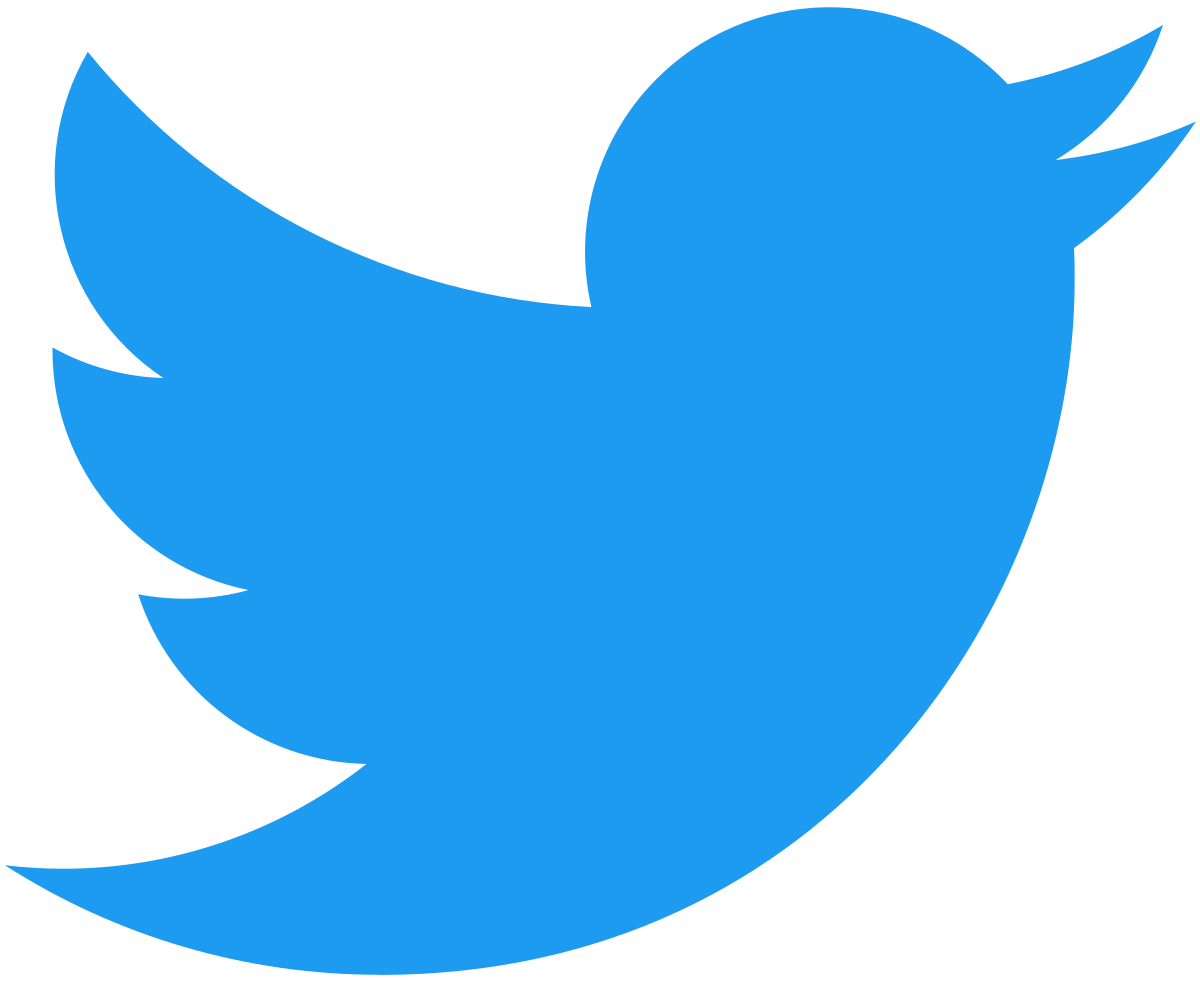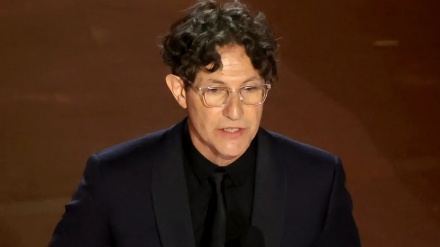視点
なぜ「オッペンハイマー」は米国のお気に入りなのか?
-

映画「オッペンハイマー」のワンシーン
今年のアカデミー賞で作品賞を含む7冠に輝いた「オッペンハイマー」(クリストファー・ノーラン監督)。しかし、その内容が体現するのは「原爆投下は世界秩序の維持のためであり、アメリカの核保有を誤解しないでほしい」というものです。
ノーラン監督はこの作品で、伝えたいことを冒頭でほぼすべて描写し、残りの部分はその主張の解説・補強に充てています。
アメリカが歴史上、世界で犯してきた犯罪には枚挙に暇がありません。その一部は科学技術の発展によってもたらされました。アメリカは権力を信奉し、抑止力もその一環として考えてきました。科学技術がアメリカの権力のために利用されてきたことは、「オッペンハイマー」の中でも明瞭に描かれています。

こうした視点から「オッペンハイマー」を鑑賞すると、アメリカ社会の対立・論争が見えてきます。その対立とは、一人の政治家と一人の科学者の対立です。ノーラン監督が描くのは、科学者が原爆を製造し、政治家がそれを投下する社会です。それは、科学者が後悔や苦悩にさいなまれる一方で、政治家が原爆の使用をアメリカの戦略として正当化する社会、「非人道的行為」が苦渋に満ちつつも現実を直視した戦略であると語られる社会です。
この映画は、政治家が自らの地位を悪用して権力を追求することは悪だが、原爆そのものや開発者を悪く言うべきではないと訴えます。なぜなら、原爆が戦争の継続を不可能にし、結果として自国の兵士の命を救うからです。そういう意味で、科学者は原爆開発という使命を負い、政治家はその使用を決断しなければならないとされるのです。
その一方で、人間の命の重さをどのように測るのか、なぜ年月を経ても原爆投下について誰も謝罪しないのかという問いは見られません。
映画がとる立場は、「この世界には新たな秩序を拒む邪悪な勢力が常におり、我々はそれらを退治したのだ」というものです。そして映画を見る者にも、その「新たな秩序」を受け入れるよう迫ります。その秩序とは打算的なものであり、倫理的・人道的なものではないのです。

「オッペンハイマー」は複雑なストーリー展開で、観客にとっては気楽に楽しめる映画ではありません。しかしノーラン監督はこの手法を通じて、観客を数多くのエピソードや論争にいざない、秩序を壊しては、別の秩序を創り出すことに成功しています。
「オッペンハイマー」のメッセージは、原爆投下に対する国際社会からの批判に「仕方がなかった」と言っていることに尽きます。彼らは、頭の中のアメリカがそうした批判に常に対抗しなければならないという強迫観念を抱いているのです。
アメリカの原爆開発は当初ナチス・ドイツを念頭に進んでいましたが、ドイツが降伏してもストップすることはなく、最終的に日本に投下されるまで続きました。映画では、「科学的成果」とされた原爆開発が、戦後のソ連の脅威を理由に再び「仕方がない」ものとされる様を描いています。

劇中には、原爆開発者であるオッペンハイマーが当時の米大統領に対し、自分の手が血で汚れていると感じていると語るシーンがあります。それは、それでも原爆が世界を救い、平和をもたらし、日本に投下されたことで誰も不幸にはなっていないという論理に回収されていきます。
映画は、「核兵器は戦争兵器として使われるべきではない」というメッセージを出しますが、それは結局は、「核兵器はアメリカの特権であり、他国は持つべきではない」というものです。
「オッペンハイマー」は、数十万人を殺害した原爆投下という非人道的行為を、一人の科学者の感情と時の政治判断の間を往復することで「仕方がなかった」ものとして釈明する危険性をはらんでいます。